はじめに
認知症の看護の基本は、患者のQOLを保ち、その人らしく暮らせるように支援すること。
患者に適した看護ケアは、興奮や不安などのBPSD(周辺症状)を減少できるとされているので、患者の言動の意図や心情を理解し、対応することが重要となる。
認知症の情報収集と観察
症状(中核症状)
- 記憶障害
- 失語・失行・失認
- 遂行(実行)機能障害
- 見当識障害の有無や程度
周辺症状(BPSD)
- 徘徊
- 幻覚・妄想
- 暴言・暴力
- 焦燥性興奮
- 異食・過食
- 抑うつ・不安
- 性的脱抑制
栄養状態
- 食事の摂取状況
(過食・異食の状況) - 食事摂取量
- 水分摂取量
- 栄養状態を示す血液データ
- BMI・体重変動など
ADL
移動状況
身体機能の低下や薬剤の影響や、ふらつきや立ちくらみなどのが出現するほか、注意力の低下や危険回避能力の低下により、転倒・転落を起こしやすい状況となりうるため、歩行状況を確認する。
排泄
排泄機能に問題がなくても、認知機能・身体機能の低下により排泄行動に支障がでる場合もあるので、排尿・排便回数や性状、失禁の有無を観察する。
周囲の環境・安全
- 危険物や障害物はないか
- 目印などわかりやすい環境か
- 自立を促すような環境か
- 過剰や音や刺激はないか
- 不快なにおいがないかなど
治療の効果・副作用
- 薬物療法やケアの効果
- 睡眠導入剤や抗不安薬などの副作用
(日中の眠気やふらつきなど) - 肝機能・腎機能
代謝・排泄機能の低下により薬の副作用がでやすい。また、薬の副作用として肝機能障害や腎機能障害が出現することがある。
患者・家族の理解
- 患者自身が疾患をどのように認識しているか
- 家族が疾患をどのように認識しているか
- 家族の介護負担
(不安・疲労・患者の諸症状によるダメージなど)
認知症の看護ケア
セルフケアの援助
過度な援助は、残存機能の低下させる原因となるので、患者が持っている能力を生かし、不足した部分に応じてセルフケアの援助を行う。
例えば、食事も全介助するのではなく、自助具や椅子・テーブルの高さを調整するなどして、可能な限り自分で食事をとれるよう援助する。
環境支援
安心して暮らせる工夫と、セルフケアの援助と同様に、QOLを維持するための環境づくりが重要となる。
例えば、慣れ親しんだ家具や寝具、写真を持ち込んで患者にとって居心地のよい環境を作る。
見当識の支援としては、病室やトイレなどの位置がわかりやすいように、絵や小物の目印をつけて場所がわかりやすいように工夫する。カレンダーや時計を飾ったり、照明を調整するなどして時間の見当識が維持できるような空間づくりも大切となる。
館内放送や職員の声など騒音や過度な照明や不快な臭いは、混乱を引き起こし、食事など日常生活動作に集中できなくなってしまうので注意する。
リハビリテーション
認知症は脳細胞が進行性に死滅するため、失われた機能が戻すことは難しいが、リハビリによって脳を活性化して残存機能を維持・向上させると言われている。
回想法や音楽療法・作業療法・運動療法など各種のリハビリがあるが、他者とコミュニケーションをとりながら、患者が心地よい程度に行うことが大切である。
回想法とは?
心理療法のひとつで、過去の思い出を語り合ったり、話すことで脳が刺激され、精神状態を安定させる効果があるもの。
適切なコミュニケーション
認知症をもつ患者は、通常のコミュニケーションが困難になため、その能力を補いコミュニケーションを図ることが介助者の重要な役割となる!
そのため、認知症患者とコミュニケーションをとるためには、事前に情報収集など必要な準備が重要となる。
コミュニケーションの準備
- 静かな場所を用意する
- 補聴器や眼鏡をつけてもらう
- 患者の原因疾患や重症度を理解する
- 患者の嗜好・環境・生活リズムなど生活環境を理解する
- 患者の職業や家族背景を理解する
効果的なコミュニケーション
- 正しい言葉遣いをする
- 視線を合わせ、引くめのトーンでゆっくり・はっきり話す
- 簡単な語を使い、短い文章で話す
- 質問は一度にひとつ
- 患者のペースで話し、答えるための時間を十分に与える
- 相手の話を途中で遮らない
- 間違ったことを言っても否定・訂正をしない
- 説得より納得いくように話す
- 患者の非言語的なコミュニケーション(表情やしぐさ)にも注意を払う
- 昔の話を引き出す
家族・介護者への援助
認知症と診断された患者の家族は、疾患や症状、介護について不安を感じていることがある。まず認知症に対して不足している情報は、看護師や医師から提供し、不安の軽減に努める。
介護負担については、理学療法士などと連携をはかり、自宅での生活を想定したリハビリを行う。また、利用できる社会資源を提案し、介護支援を依頼する。
BPSDへの対応方法
徘徊している
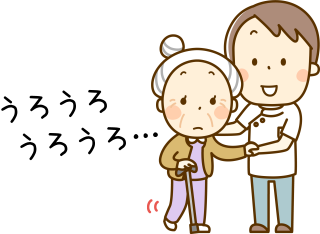
うろうろと歩きまわっている場合でも、何かを探していたり、目的があって歩いている場合もある。まずは、「どうされました?」「気になることがありましたか?」と声をかけて、静かで落ち着く場所で話を聞く。
目的がない場合は、行動を抑制すると余計に興奮することもあるので、転倒などの事故防止のための安全対策を取ったうえで、気が済むまで歩いてもらうか、一緒に歩いて話題を変えながら帰室を促す。
家に帰りたい・会社に行きたい…
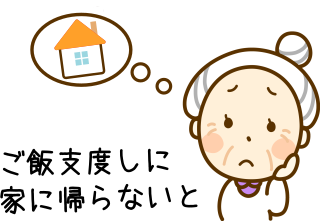
「家にに帰りたい」「会社に行かないと」など落ち着かなくなることがある。
このとき、「入院中で帰れない」「退職しているから会社には行かなくていい」と否定してしまうと、不安が増強し、興奮する患者も多い。
今いる場所が居場所であること、安心できる場所だということを伝えたり、「迎えが来るまで一緒に待ちましょう」などと理由をつけて延期する対応をとる。
異食がある
認知症患者は食べ物ではないもの、例えば身の周りにあるゴミやせっけんなどを食べたり、かじったりすることがある。物によっては、中毒や窒息を起こすこともあるので、注意しなければいけない。
異食がみられる患者には、まず危険なものを口に入れないよう環境を整えたり、生活の様子を見守るようにする。
もし異食行為を目撃した場合、大きな声を出すと驚いて飲み込んでしまう場合があるので、出来るだけ穏やかに「出してください」と声をかける。
患者の好物を見せて、「こちらを食べませんか?」と促して、口の中のものを出してもらうのも効果的な方法。
過食

ご飯を食べたことを忘れてしまったり、満腹中枢の機能低下により目につくものいくらでも食べてしまうことがある。
特に脳血管性認知症では栄養の偏りや肥満によって脳卒中再発のリスクが高まるため、注意が必要となる。
例えば、食事をしたら、患者本人に食べたものを記録してもらったり、食べたというサインをもらうなど、食事の記録を残して、忘れた時に記録をみてもらう。また、1度の食事を小分けにしたり、嚥下に問題がなければ噛み応えのある形態にするなど、工夫をする。
日常生活でも、食事に固執しないようにリハビリや気分転換の時間を取り入れるのも有効とされている。
暴言・暴力がある
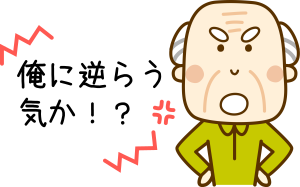
攻撃的になるには、体調が悪かったり、何かしらの刺激があったと考えられる。暴言・暴力に対し、介護者が興奮して叱ったり、抑制すると、自尊心が気づ付けられ、余計に興奮するので、それは避けなければいけない。
まずは、危険物を周りから排除し、気持ちを落ち着ける場所を整えたら、その場を離れて様子をみる。
興奮が落ち着いたら、体調に問題はないかチェックする。興奮の原因として介助者との関わりの中に原因があったのかもしれないため、これまでのケアを見直したり、ひどくなるようであれば、医師に相談し、薬剤の検討も必要となる。
ケアの拒否がある
日常生活動作の中でも、特に接触の多い清潔や排泄に関するケアに対して拒否が見られることが多い。
無理強いをすると、拒否が強くなったり暴力がみられることもあるため、時間をおいたり諦めることも必要となる。
ただ、服薬拒否においては命にかかわる危険性もあるので、医師に相談し、形状をかえたり、トロミのついた食事に混ぜるなど工夫が必要となる。
入浴拒否は、入浴が気持ちよいということを忘れてしまっている場合も多いので、「汗を流してさっぱりしますよ」「体が温まりますよ」とメリットを伝える。
妄想がある

妄想は被害的な妄想が多く、財布が盗まれたなどの「物盗られ妄想」や配偶者に見捨てられる、浮気しているなどの「嫉妬妄想」が代表的。
これらの妄想は、患者にとって『現実』となっているので、否定・訂正すると、さらに興奮させてしまう可能性が高い。
対象が自分であっても、否定したい気持ちは押さえて、まずは否定も肯定もせず、共感する態度で、患者の話を傾聴する。
その後、患者も一緒に財布を探すよう誘導したり、興奮している場合には、その場を少し離れて、時間をおいて対応する。

