胃がんとは?
胃粘膜上皮から発生する悪性腫瘍。
胃壁の粘膜層~粘膜下層にとどまる悪性腫瘍を早期胃がん
胃壁の固有筋層まで達する悪性腫瘍を進行胃がんに分類される。
胃がんの原因
胃がんの危険因子
胃がんの発生機序は明らかとなっていないが、食事(高塩分)、喫煙、糖尿病、肥満は胃がんの発生に関与していると考えられている。
ヘリコバクター・ピロリ感染
胃粘膜が胃炎や萎縮を起こすと、胃の粘膜が腸の粘膜のように変性する、腸上皮化生(ちょうじょうひかせい)が発生し、そこから胃がんへと移行するとされている。
この腸上皮化生が発生する原因として、ヘリコバクター・ピロリ菌(H.pylori)の長期感染が関係することが明らかになっている。
H.Pyloriは、潰瘍の原因にもなる菌で、感染に気が付くことが出来れば、内服治療で除菌することができる。
胃の解剖学的区分
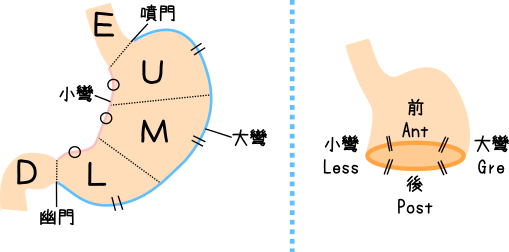
胃は、小彎(しょうわん)と大彎(だいわん)をそれぞれ3等分にし、ぞれぞれを結んで3つの領域に分けられる。
U:上部
M:中部
L:下部
(E:食道)
(D:十二指腸)
また、胃の全周は、前・後・小湾・大湾の4つの領域に分けられる。
検査結果や医師のカルテでは、略語で病変部位が記載されていることが多いので、ノートなどにまとめて、確認できるようにしておく!
前壁:Ant
後壁:Post
小彎側:Less
大湾側:Gre
全周:Cire
→『胃・十二指腸の構造と働き』を詳しく見る
胃がんの分類
肉眼的分類
胃癌のステージ分類は、生検の結果など総合的に評価しなければいけないが、肉眼的分類は、X線検査や内視鏡などの肉眼的所見から早期に判定でる。
病期は、0型~5型の6つに分類でき、0型(表在型)は、さらに5つに分類される。
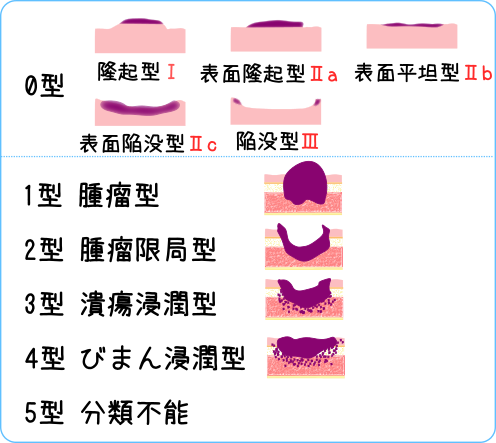
胃壁の深達度による分類
胃壁の深達度(深さ)を表すものとして、T分類という分類方法がある。
『胃がんの取り扱い規定』により、カルテ等には、これまた略語で記載される。
T1:粘膜(M)・粘膜下層(SM)にとどまるもの
T2:固有筋層(MP)・漿膜下層にとどまるもの
T3:漿膜に接しているか、腹腔に露出しているもの
T4:他臓器転移に浸潤しているもの
TX:分類不能
M・SMまでのT1だけは、早期胃がんに分類されるが、MPまで深達するT2以上はすべて進行胃がんに分類される。

ステージ分類
がんの深達度(T分類)や、リンパ節転移の数から総合的に、胃がんのステージが分類され、治療方針が決定する。
胃癌の病期は、ⅠA、IB、ⅡA、ⅡB、ⅢA、ⅢB、ⅢC、Ⅳの8つに分類される。
| リンパ節転移 深達度 | N0 なし | N1 1~2個 | N2 3~6個 | N3 7個以上 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | ⅠA | ⅠB | ⅡA | ⅡB |
| T2 | ⅠB | ⅡA | ⅡB | ⅢA |
| T3 | ⅡA | ⅡB | ⅢA | ⅢB |
| T4(SE) | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅢC |
| T4(SI) | ⅢA | ⅢB | ⅢC | ⅢC |
| 肝・肺・腹膜 遠隔リンパ節に転移 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
胃がんの症状
早期胃がん
症状がないことが多く、検診で発見される場合が多い。
症状がある場合は、潰瘍に伴う心窩部痛や上部不快感などの訴えが多い。
進行性胃がん
- 食欲不振
- 腹部膨満
- 上腹部の違和感や痛み
- 体重減少
- 腫瘍からの出血により黒色便、貧血症状
- 腹部から触知できる腫瘤
- 転移による腹水・黄疸など
胃癌の転移経路
リンパ節転移
がんがリンパ管に湿潤すると、リンパ管を通って、遠隔の臓器へ転移する危険性がある。そのため、進行胃がんの場合、胃の周囲だけではなく、胃の後ろや膵周囲のリンパ節も切除するのが基本となる。
血行性転移
リンパと同じく、血液に乗って胃につながる臓器…例えば肝臓や肺、皮膚、脳などに転移する危険性がある。
腹膜転移
胃で発生したがんが進行すると、胃壁の外側まで浸潤し、腹腔内にがん細胞がまき散らされる。この状態は、種を巻くように多数のがんの塊が認められることが多いため、腹膜播種(ふくまくはしゅ)とも呼ばれる。
1個でも腹膜転移が発見された場合には、腹腔内にたくさんの『がんの種』があることを意味しているため、ステージⅣと診断でき、完治する可能性はほぼゼロとなる。
胃癌の治療
内視鏡的治療
EMR(内視鏡的粘膜切除術)
適応:深達度T1の中でも、粘膜(M)にとどまる2㎝以下のがんが適応。
方法:内視鏡を挿入し、生食でがんを隆起させ、ワイヤーをかけて焼却切除する。
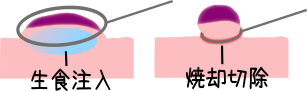
ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)
適応:粘膜(M)にとどまるがんで、EMRでは切除が難しい大きい腫瘍が適応。
方法:内視鏡を挿入し、EMR同様に、生食などの薬液でがん隆起させ、電気メスで粘膜下層を観察しながら、腫瘍を剥離、切除する。
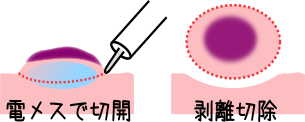
外科的治療
胃全摘術
がんが胃全域に及んでいる場合や、リンパ節転移が多く、幽門や噴門を残すのが不適当な場合に行われる手術で、再建方法はいろいろあるが、ルーワイ法が最も用いられる。
この時、リンパ節郭清を目的として、脾臓を同時に摘出することがある。
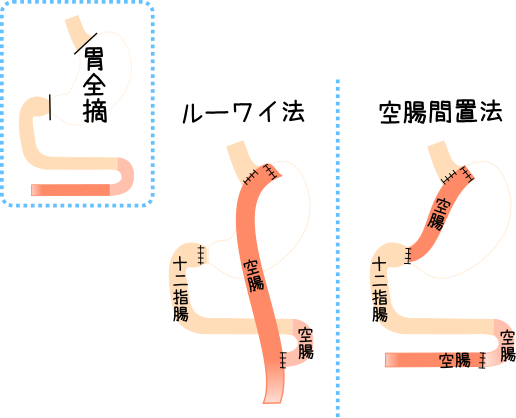
幽門側胃切除術
がんが胃の下部・中部に限局しているもので、根治手術を目的として胃の2/3切除とリンパ節郭清を行う。
最も多く用いられる再建方法は、残った胃と十二指腸を直接つなげるビルロードⅠ法と、空腸をつなぐルーワイ法。
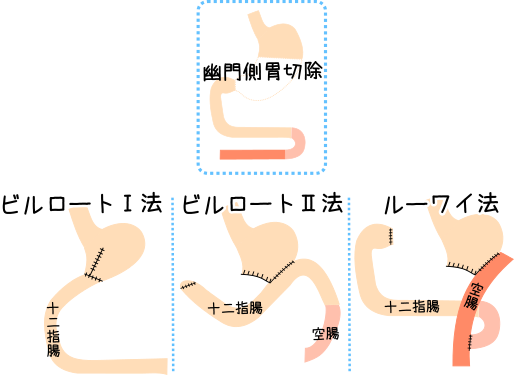
噴門側胃切除術
胃の上部に限局するがんの場合に行われる手術で、胃の1/2程度を切除する。
再建方法は、食道の残った胃を直接つなげる方法があるが、逆流性食道炎をおこしやすいため、食道と胃の間に、空腸を一部もってきて繋げる空腸間置法を行うことが多い。

拡大手術
胃のみならず、胃の遠くのリンパ節や膵臓、脾臓、大腸、肝臓などの広い範囲を切除する方法。
リンパ節転移が多かったり多臓器への浸潤がある場合、根治するために行われる。
姑息的手術(こそくてきしゅじゅつ)
がんの根治が不可能な場合に、症状の改善や延命目的で行われる手術のこと。
もちろん全身状態や生存期間なども考慮して、必要だと判断された時のみ行われる。
経口摂取が困難な場合や転移で腸閉塞を起こしている場合には、バイパス術が行われたり、延命に目的で、がんの減量手術(がんを出来る限り切除する手術)を行う場合がある。
化学療法
延命のための化学療法
手術適応のないステージⅣや、手術してもがんが残っている場合には、延命のために、化学療法を行う。
術後補助化学療法
根治切除が行えても、ステージⅡ~ⅢA、Bの場合、術後1年間TS-1(抗がん剤)を内服する。内服した場合には、5年生存率が70%→80%になることが明らかになっている。
胃切除後の観察と看護
術後合併症の観察
胃切除だけに限らないが、手術の侵襲により、呼吸器合併症、術後出血、腸閉塞、縫合不全などの術後合併症を起こす危険性があるため、それぞれのリスクが高い時期は、特に注意深く観察する。
胃切除後は、膵液漏に注意する
胃切除では、術中操作により膵臓を損傷し、膵液漏を起こす危険性がある。
膵液は消化作用があるため、放置しておくと周囲の組織を融解し腹腔出血を起こすこともある。
そのため、ドレーン排液や腹部症状を観察することが重要で、ドレーン排液が白濁または、赤ワイン色に変化したり、すっぱい臭いがしてきた場合には、膵液漏を疑い、すぐに医師へ報告する。
腹腔ドレーン(2)観察ポイント参照
その後の対応としては、採血でアミラーゼの値測定、CT検査で確認を行うことが予測される。出血など起こしていなければ、適切にドレナージを行うことで、膵液漏はほとんど場合自然に治癒する。
ダンピング症状の観察
食事が開始されたとき、注意が必要な合併症。
胃切除後の10~30%でみられる合併症なので、ダンピング症状の予防と、症状の観察をしっかり行う。
早期ダンピング症状
食後30分以内に現れる、循環血液量低下による症状や消化器症状のこと。
今までは、胃・十二指腸で食べ物が徐々に薄まりながら消化吸収されていたが、胃切除後には、高張な(薄められていない濃度の高い)食べ物が、小腸に流れ込むため、高張液投与時と同じような原理で、細胞外液の腸への移動が起こる。
すると、循環血液量が減少したり、消化管ホルモンの分泌亢進、蠕動運動の亢進が起こり、多くの症状が出現する。
循環血液量低下による症状…眩暈・冷汗・倦怠感・動悸・頻脈など
消化器症状…下痢、悪心・嘔吐、腹痛、腹部膨満感など
後期ダンピング症状
食後2~3時間で出現する低血糖症状のこと。
胃切除後は、急速に小腸に食べ物が流れ込むため、糖分(炭水化物)を多く摂取した場合には、一過性に高血糖状態となり、それに伴いインスリン分泌が亢進する。インスリンがしばらく出続けている間に、低血糖になってしまい症状が出現する。
低血糖症状…脱力感、めまい、冷汗、頭痛、手指の痺れなど
ダンピング症状予防のための対応
- 高タンパク、高脂質、低炭水化物を基本
- 1回5~6回に食事を分ける。
(胃切除後用の食事メニューが各施設であるはず) - ゆっくりよく噛んで1回30分以上かけて食べるよう指導する
- 冷たいものは避ける
- 食後1時間は、小腸への急な流入を防ぐため、安静臥床が基本となる。
※逆流性食道炎を起こしているときは、食道に逆流するのを防ぐため、臥床しない。 - 後期ダンピング症状(低血糖)を起こした場合には、飴玉などをひとつ摂取してもらう。
逆流性食道炎の観察
手術で、今まで逆流を防いでいた噴門や幽門が切除されると、胃液・膵液・胆汁などの消化液が食道に逆流しやすくなる。
消化液が食道に逆流すると、炎症を起こし、胸やけ・背部痛・心窩部痛・嚥下障害などの症状が出現するため、食事摂取も困難になってしまう。
逆流性食道炎が起きた場合には、食直後はもちろん、就寝時も臥床は避ける必要があり、セミファーラー位をとるよう指導する。
内科的治療として、プロトンポンプ阻害薬やH₂ブロッカーを投与する場合があり、症状が強い場合には、逆流防止のため再手術を行う場合も稀にある。

